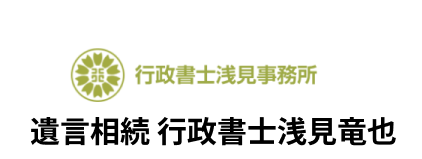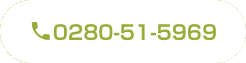遺産分割完了後の認知によって相続人となった者
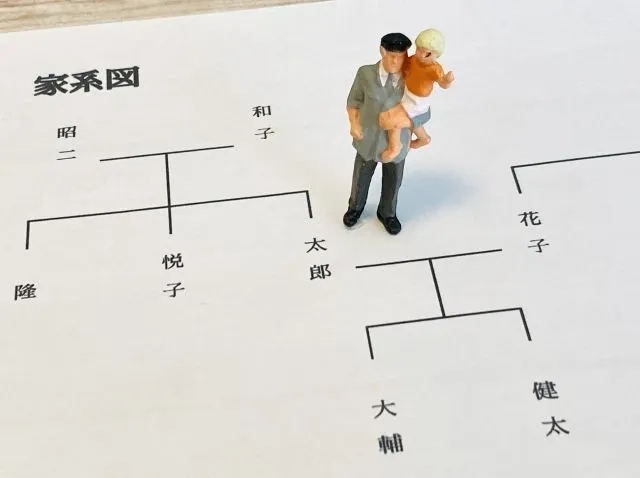
事例
被相続人Aが死亡し、その法定相続人であった配偶者B及び長男Cが被相続人Aの遺産について遺産分割協議を成立させました。その後、認知の訴えに係る判決の確定によって被相続人Aの子として原告Xが認知されたため、XはAの相続人となりました。そこで、原告Xは、Aからの法定相続分に相当する価格の支払を求めて、長男Cを被告として民法910条に基づく価額支払請求訴訟を提起しました。
分かりやすく言うと、父が亡くなり遺産分割が終わったあと、隠し子Xから訴えられて子と認知されたX相続人の遺産分割をどうするかというお話です。
裁判では、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額について、積極財産の価額から消極財産の価額を控除すべきか否かが争われました。
前提として民法910条は、「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
ではその価格は積極財産から消極財産を控除したものなのでしょうか?
最高裁の判断は
「民法910条の規定は、相続の開始後に認知された者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときには、当該分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることによって、他の共同相続人と認知された者との利害の調整を図るものである(最高裁平成26年(受)第1312号、第1313号同28年2月26日第二小法廷判決・民集70巻2号195頁)。そうすると、同条に基づき支払われるべき価額は、当該分割等の対象とされた遺産の価額を基礎として算定するのが、当事者間の衡平の観点から相当である。そして、遺産の分割は、遺産のうち積極財産のみを対象とするものであって、消極財産である相続債務は、認知された者を含む各共同相続人に当然に承継され、遺産の分割の対象とならないものである。
以上によれば、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、当該分割の対象とされた積極財産の価額であると解するのが相当である。このことは、相続債務が他の共同相続人によって弁済された場合や、他の共同相続人間において相続債務の負担に関する合意がされた場合であっても、異なるものではない。」
要約
簡単に言えばプラスの財産からマイナスの財産を引いたものを分割の対象とするものではなく、プラスの財産のみ分割の対象とします。
マイナスの財産は可分債権として当然に相続人に分割され、そもそも負債については遺産分割の対象とされていないからということです。